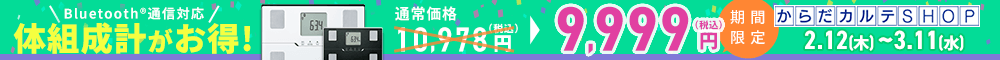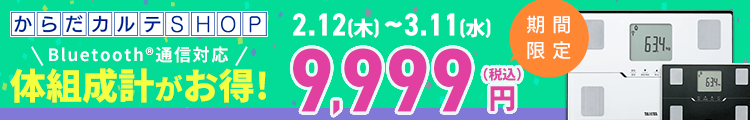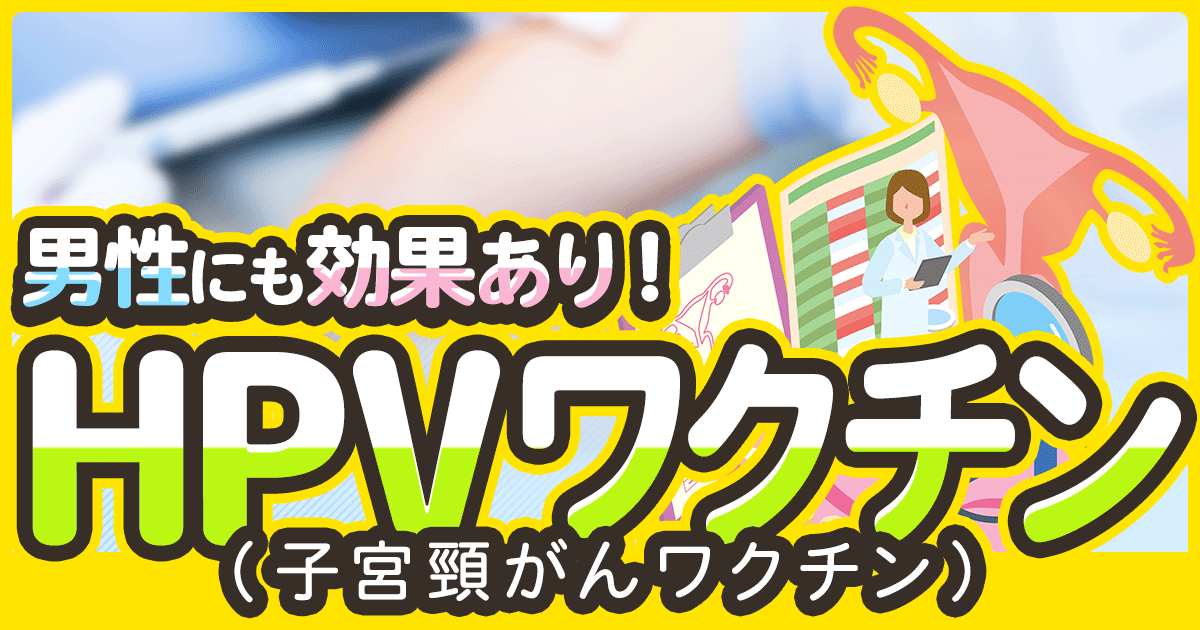女性や高齢者に多い便秘を「食べること」で解消しよう!
2020/10/13 掲載

厚生労働省の国民生活基礎調査によると、男性に比べて女性の方が便秘の自覚症状がある人が多く、男女ともに高齢になるほど増加しているという結果が出ています。
特に女性では、20代から50代では40%程度、60代では45%、70代では80%以上が便秘であると回答しています。(※1)
皆さんのお腹のコンディションはいかがでしょうか。
慢性の便秘の定義
慢性の便秘は、『本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態』と慢性便秘症診療ガイドラインで定義されています。
毎日出ていなかったとしても、排出すべき量を快適に排便できていれば便秘ではないと言い換えることができます。
毎日出ていないから便秘だと思っていた方は、出ない日数を数え続けるのではなく、便の状態や快適に排便できたかということへ意識を向けてみるのもおすすめです。
そして便秘にならないために出来ること。便秘は運動習慣にも関係があるので、可能な範囲で運動や活動量は維持・増加させていただけるのが良いのですが、運動はちょっと……という方は、まず運動以外で手軽に出来ることを実践してみましょう。
では、運動以外で便秘改善のためになりそうなことと言えば、やはり真っ先に思いつくのは食事ではないでしょうか。
食生活からの便秘改善
バランスの良い食事

主食・主菜・副菜を揃えて、炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル、食物繊維を適度に摂取することは、便の量を増やすことにも繋がります。食事量が少なければ便の量も少なくなってしまいます。
近年話題の炭水化物制限をされている方もいらっしゃると思いますが、炭水化物を極端に減らし過ぎると食物繊維の不足にも繋がります。
また、脂質も私たちのからだには必要不可欠です。脂質に含まれている脂肪酸が大腸の粘膜を刺激して蠕動(ぜんどう)運動を促進してくれます。
減量のために炭水化物や脂質を控えて便秘が続くという方は、炭水化物や脂質の摂取が少な過ぎるかもしれません。
水分補給

大腸では水分や電解質(カリウムやナトリウムなど)が吸収されます。便秘で大腸に便が留まっている状態では、便中の水分がどんどん吸収されてしまい便が固く出にくくなってしまうので、こまめな水分補給を意識しましょう。
摂取する水分は、食事に含まれる水や飲料水、栄養素が代謝して得られる代謝水などがあります。排泄は、尿や便、汗、呼気などから水分を失っていきます。起床後、朝食、昼食、夕食、入浴前後、就寝前と、食事と食事の間もこまめな水分補給を心がけましょう。
運動習慣のある方は、運動前・中・後の摂取と合わせて、水分補給の内容も運動強度や運動時間に合わせて調整しましょう。
食物繊維

便秘に悩んでいる方は既に食物繊維の摂取を意識されている方も多いと思います。食物繊維には水溶性と不溶性があり、食物繊維をしっかり摂っているのに便が固いという方は、不溶性の食物繊維が多く、摂り方が偏っている可能性もあります。
便秘気味の方には水溶性食物繊維がおすすめです。水溶性食物繊維は、水に溶けてドロドロになるため固くなった便に水分を与え、排泄しやすくしてくれます。
ただ、ほとんどの食品は不溶性食物繊維、水溶性食物繊維のどちらも併せ持っているため、食物繊維が豊富な食品を意識して摂ることで不溶性・水溶性食物繊維の摂取に繋がります。(表1)
【表1】食品に含まれる不溶性と水溶性の食物繊維
| 食品名 | 1回の摂取目安量 | 不溶性食物繊維 | 水溶性食物繊維 | 食物繊維総量 |
| 玄米 | 150 | 1.8 | 0.3 | 2.1 |
| そば | 170 | 2.5 | 0.8 | 3.4 |
| さつまいも | 100 | 2.4 | 1.1 | 3.5 |
| じゃがいも | 100 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| 大豆 | 50 | 2.9 | 0.5 | 3.3 |
| おから | 50 | 5.5 | 0.2 | 5.8 |
| ごぼう | 50 | 1.7 | 1.4 | 3 |
| ブロッコリー | 60 | 1.7 | 0.5 | 2.2 |
| オクラ | 40 | 1.4 | 0.6 | 2.1 |
| えのきだけ | 40 | 1.4 | 0.2 | 1.6 |
| ぶなしめじ | 40 | 1.4 | 0.1 | 1.5 |
| ひじき | 5 | 表記なし | 表記なし | 2.6 |
| めかぶ | 40 | 表記なし | 表記なし | 1.4 |
| りんご | 85 | 0.8 | 0.3 | 1.2 |
| キウイフルーツ | 70 | 1.3 | 0.5 | 1.7 |
単位:g
表1を見ると、おからは食物繊維を多く含みますが、その内訳をみると不溶性が水溶性より極端に多いことが分かります。便秘解消のためにおからを食べているのに、なかなか便秘が解消されないという方は、不溶性の食物繊維の摂取に偏っているかもしれません。
食品の多くは不溶性の食物繊維の方が水溶性より多く含まれますが、ごぼうのように不溶性と水溶性が同じくらい含まれているものもあります。もし不溶性に偏っていたという方は、水溶性の食物繊維の摂取を意識してみることをおすすめします。
オリゴ糖

オリゴ糖には便を緩くする働きと腸の動きを活発にする働きがあります。また、ビフィズス菌や乳酸菌の増殖促進の作用により腸内フローラ(腸内細菌の集まり)の改善に繋がるといわれています。動物性たんぱく質に偏った食事バランスだと腸内に悪玉菌が増えやすくなるといわれています。
善玉菌をふやすためには、食事バランスを整えることや善玉菌(乳酸菌、ビフィズス菌など)や善玉菌のエサになるもの(食物繊維やオリゴ糖など)を摂ることがおすすめです。スーパーやドラッグストアで手軽に購入ができ、比較的低カロリーなので、砂糖の代わりに料理に使用するのもおすすめです。ただ、便を緩くする働きがあるため、使用量などはパッケージなどの表示を確認し、摂り過ぎには注意しましょう。
ここまで4つポイントをお伝えしてきましたが、これさえ食べていれば、飲んでいれば大丈夫!という食材はありません。自分のお腹のコンディション、便の状態(形態)を観察し、改善できそうなことがあれば実践してみてください。
女性ホルモンとの関係
冒頭で男性よりも女性に便秘が多い傾向があることをお伝えしました。その原因の一つに女性ホルモンが関わっています。
女性には月経サイクルがあり、そのサイクルに合わせて女性ホルモンが変化しています。
女性ホルモンの中でも黄体ホルモン(プロゲステロン)という排卵後から分泌量が増加してくるホルモンが腸の働きを抑えるため、月経前になると便秘しやすくなるのです。
最後に、便秘は食事の偏りや水分の摂取不足、運動不足など原因はさまざまです。
食事や運動以外に、ストレスも関係があると言われていますので、食事バランスの見直しや、生活の中での活動量を確保することと合わせて、ストレスマネジメントもオススメです。
男女ともに20代から50代では半数程度の人が『悩みやストレスがある』と回答している(※1)ことからも、ストレスとの向き合い方もポイントになりそうですね。
【参考文献】
※1 厚生労働省 平成28年 国民生活基礎調査